|
おおまかではありますが、書体の種類、帳票デザインにおける書体の選び方の基本についてお分かりいただけたかと思います。
さて、「見る(見せる)文字」を使ってデザインすると言っても、現在のパソコンによるデジタル制作環境下で、実際に多数の書体を目の前にして、それらをどのように帳票制作に活かしていけば良いのでしょうか。
書体選びのコツ
様々な種類が存在する書体ですが、やはりその中でも伝統的なもの、オーソドックスで読みやすいものは、明朝体、ゴシック体です。これに対し色々な個性を備える新書体は、現代的なイメージやPOPなイメージ、コミカルなイメージなど、様々なイメージを演出することが可能です。
帳票にはそれぞれの用途・目的というものがありますから、ビジネスの場で使われるものから、家庭で使われるもの、官公庁向けから現代的デザインの求められるものまで、それぞれの使用環境を想定してデザインされなければなりません。よって、帳票デザインにおける書体のスタンダード、この書体がお勧めなどというものは無く、その時々の使用目的に合った選定がなされるべき、と言うことができるでしょう。
ただし、毎回繰り返しになりますが、見やすさ、使いやすさを第一に考えなければならないことは言うまでもありません。しかし、最近の雑誌などにおいては、デザイン的な面白さやカッコ良さを狙った書体の扱いが多く見受けられ、結果として大変読みにくいものとなっているのです。
それでは、読みやすいデザインを考えた、書体選びのポイントとはどのようなことでしょうか。
読むという類のものではなく、結果ラインがきれいに揃っていた方が洗練されてスッキリしたデザインとなるからです。
1.1つの帳票には3書体まで
項目名の書体をブロックごとに変えるとか、重要度別に変えるなど、1つの帳票で色々な書体を使いすぎると、雑然として統一感の無いデザインになります。これは前回の「ケイ線」と全く同じで、見やすさを考えるなら書体の種類は、タイトル、項目名、その他(メッセージ、注意書きなど)の3種類位にとどめるべきです。その上で重要度などの区別をつけたい場合は、書体のサイズで変化をつけましょう。
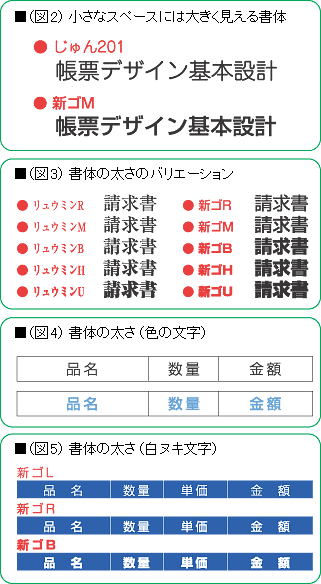 2.小さなスペースに小さな文字を使用するときは、同サイズでも大きく見える書体を選ぶ
(図2) 2.小さなスペースに小さな文字を使用するときは、同サイズでも大きく見える書体を選ぶ
(図2)
狭いスペースに文字を入れたい場合は、新書体系のじゅんや、新ゴなどの、文字サイズの正方形一杯を使ってデザインされている書体を使いましょう。
3.帳票の使い手・演出意図によって太さを考える(図3)
お年寄りを対象とした帳票なら太い書体、オフィス向けで落ち着いた雰囲気を求められるなら細い書体、といった使い分けが必要でしょう。
また細い書体はデリケートでシャープな感覚を演出でき、太い書体はダイナミックさ、力強さを演出できます。
さらに、原則的に淡い色の文字には太めの書体、スミ、または濃い色の文字には細めの書体を選ぶべきです。これはケイ線の使い方(太さの選び方)にも共通しています。(図4)
ただし、ベタや濃いアミ地に白ヌキ文字の場合には細めの書体を選ぶのが無難です。白ヌキ文字は太く見えるものです。
しかし、小さな文字の場合は、細すぎれば文字が切れるし、太すぎればつぶれてしまいます。書体の太さにバリエーションがある時は、R(レギュラー)など、中間程度のものを選びましょう。(図5)
ここまでは、書体を選ぶに当たってのポイントをご紹介して参りました。
次の段階として、文字をレイアウトするときに注意する点を考えてみましょう。
|
