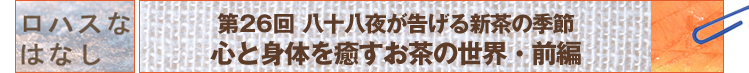|
●八十八夜のお茶はなぜ珍重されるのか?
「夏も近づく八十八夜……」の茶摘みの歌でも知られるように、八十八夜は茶摘みの季節の訪れを告げるものです。そもそも八十八夜とは日本独自の雑節(ざっせつ)のひとつ。「八十八夜の別れ霜」ともいうように、農業の大敵である遅霜の心配がなくなる変わり目とされています。いよいよ茶摘みシーズンも本番というわけですが、実際には南北に長い日本列島ですから茶摘みが始まる時期は産地によって千差万別。例えば日本で一番早い鹿児島では4月の上旬(場所によっては3月下旬)から、また日本一の生産量を誇る静岡は4月20日ごろから収穫が始まります。この時期のお茶が新茶、いわゆる一番茶に当たります。
一番茶ということは、当然ながら二番茶、三番茶もあります。お茶の木は生命力が強く、4〜5月に新芽を摘んでも、1カ月もするとまた新芽が出てきます。そのため一般的にお茶は年に3回、鹿児島や静岡では4回も収穫期を迎えるのです。静岡を例にとると、一番茶(新茶)は4月下旬〜5月上旬、二番茶は6月半ば〜下旬、三番茶は7月末〜8月上旬、四番茶は9月下旬〜10月上旬に収穫されたものとなります。
一番茶は香りが良くうまみ成分のテアニンが豊富に含まれていて、てん茶(抹茶の原料)や玉露、高級煎茶に使われます。二番茶になるとテアニンが減って渋み成分のカテキンが増すため苦みが強くなり、三、四番茶と進むほどに味も香りも劣ってくるとされています。
また、茶摘みは機械で行うのが主流になったとはいえ、4〜5月のやわらかい新芽だけは、貴重品ということもあり昔ながらの手摘みで収穫されることが多いようです。手摘みは新芽の先の方(一芯二葉もしくは三葉)だけを摘み取ることができるため、味も香りもその良さが一段と上がります。
とかく初物を愛する日本人ですが、八十八夜の一番茶は含まれる成分や収穫方法の違いが香りと味の良さを生むため、高級品として珍重されているのです。
●お茶の種類を知って正しく選ぶ
ひと口にお茶といっても、茶葉の育て方や製造方法によってさまざまな種類があります。例えば煎茶や玉露は、収穫した茶葉をすぐに蒸して揉みながら乾燥させて作ります。では両者の違いは?と言うと、茶葉の育て方にあります。玉露のお茶の木は、一番茶の新芽が伸びる時期によしずなどで覆いをして日光を遮断して育てます。こうすることで茶葉にうまみ成分のテアニンが増し、渋みの少ないまろやかな味わいになります。このようにひと手間かけられた玉露は、高級茶として扱われているのです。では、主なお茶の種類とその特長を紹介しましょう。それぞれの特長を知るとお茶を選ぶ楽しみがいっそう広がります。
| 煎茶 |
日本の緑茶の8割以上を占める代表的なお茶。覆いをせずに育てた茶葉を使い、一番茶から四番茶まで味も価格もさまざま。仕事の合間など、頭をすっきりさせたい時に。
【淹れ方のコツ】少し冷ました70〜80度の湯を注ぎ、45秒〜1分ほど蒸らす。
|
| 番茶 |
硬くなった芽や大きな葉などを原料とした安価なお茶。地方ごとに独自の製法も受け継がれていて、京都の「京番茶」や徳島の「阿波番茶」などが有名。その土地だけの味を知る楽しみも。 |
| ほうじ茶 |
番茶や下級煎茶を強火で炒って香ばしさを引き出したもの。炒る工程でカフェインが昇華されるため苦みが減り、おなかにも優しい。小さい子どもやお年寄りでも飲みやすい。すっきりとした後味なので食後の一杯にも。
【淹れ方のコツ】番茶もほうじ茶も沸騰したお湯を注ぎ、15秒ほどサッと蒸して注ぐ。 |
| 玉露 |
うまみ成分テアニンを豊富に含む茶葉で作る高級茶。まろやかな味わいで、ぜいたくな気分を味わいたい時やリラックスしたい時に最適。
【淹れ方のコツ】湯量は控えめにして、2分半〜3分ほどしっかり蒸らす。湯温は50〜60度程度と低めに。 |
| てん茶 |
玉露と同じように日光を遮って育てた茶葉を、蒸した後に揉まずに乾燥させて作る。これを挽いて粉にしたものが抹茶になる。 |
●自分好みの産地を探す愉しみ
最後に日本各地のお茶の名産地を見てみましょう。お茶の味は自然条件に大きく左右されるため、宇治の抹茶、静岡の煎茶、八女の玉露など産地ごとに特長が際立っています。いろいろな産地のものを飲み比べてみるのも一興。好みの茶葉を丁寧に淹れてほっと一服……。心がじっくりと満たされていきます。
■代表的な産地とその特長■

村上茶
(新潟県) |
茶の栽培の北限地。煎茶は渋み成分が少なく、甘みが強い。 |
狭山茶
(埼玉県) |
色は静岡、香りは宇治、味は狭山と言われるように深い味わいが特長。 |
静岡茶
(静岡県) |
生産量日本一。香り高い天竜茶、深蒸しの掛川茶など銘柄茶も多い。 |
西尾茶
(愛知県) |
抹茶の原料・てん茶では日本一の産地。深い緑色、上品な香りをもつ。 |
伊勢茶
(三重県) |
うまみ成分テアニンを多く含むかぶせ茶で知られる。生産量は第3位。 |
宇治茶
(京都府) |
てん茶や玉露など高級茶が手摘み中心に作られている。 |
八女茶
(福岡県) |
お茶づくりに最適の気候に恵まれた、名産地が誇る日本一の玉露。 |
嬉野茶
(佐賀県) |
釜で炒る中国式の製法を取り入れた蒸製玉緑茶が有名。渋みが少ない。 |
知覧茶
(鹿児島県) |
全国第2位の生産地。日本一早い新茶で知られる。 |
<参考文献>
『日本食品大事典』(医歯薬出版)
春日一枝著『食べるお茶の本②』(大空出版)
三越著『日本を楽しむ年中行事』(かんき出版)
|